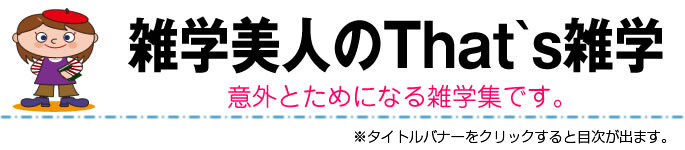■『名字』と『苗字』の違い
『名字』は、地域や区画等、所有地に由来する言葉で、平安時代から存在します。『苗字』は、血統や血族に由来する言葉で、江戸時代に作られたものです。
■ 炭酸飲料『ホッピー』とは
『ホッピー』は、本物のホップ(アサ科のツル性多年草)を使用したビールの代用品かつ、ノンアルコールの炭酸飲料です。ホッピーに焼酎で割って飲むのが、一般的です。
■ ダーツボートの起源
14世紀の百日戦争時、酒場でイギリス兵が、空のワイン樽の底に矢を投げつけたことが始まりとされています。やがて、ワイン樽の底から丸太の輪切りに変わりました。
■ 梅雨『つゆ』と『ばいう』の違い
熟語である梅雨の『ばいう』は音読みで、『つゆ』は訓読みです。この違いは、音読みは中国で使われる読み方で、訓読みは中国語に日本語を当てはめた読み方なのです。
■ 本が濡れたら…冷凍庫で凍らせよう!
雨や結露等で濡れてごわごわになった本は、ジップロク袋に入れて冷凍庫で24時間凍らせます。冷蔵庫から取り出した後、重しを乗せて乾かすと、綺麗な頁が復活します。
■ マーク装着の車を保護する!
初心者や身体障害者マーク等を装着した車は、熟練運転者が保護する義務があります。その車に幅寄せや割り込みを行うと、『初心運転者等保護義務違反』で罰せられます。
■ 対抗心で生まれた玩具『吹き戻し』
息吹きで遊ぶ紙製おもちゃ『吹き戻し』は、大正末期、富山の置き薬屋が薬のおまけに配った紙風船に、大阪の置き薬屋が吹き戻しで対抗した事がきっかけです。
■ 江戸の火事から生まれた『おじゃん』
昔、火事発生の際は半鐘を鳴らして周囲に知らせました。半鐘がゆっくり2回鳴る事を『おじゃん』といい、その頃は既に全焼のため、無駄になるという意味です。
■ 鶴(ツル)って食べられる?!
縄文時代の遺跡からツルの骨が出土されたことで、鶴は古くから食べられていた事が分かりました。尚、江戸時代に禁鳥制度が発令された為、現在は食べる事はできません。
■ ネット用語の『thx』って何?
ネット用語の『thx』は、英語圏のネットスラングで、『thanks(ありがとう)』の略語です。チャット等でタイピングの手間を省く為に略するようになりました。
■『無味乾燥』の意味
四字熟語の『無味乾燥』は、『面白みがなく風情がない』という意味です。この言葉は、基本的に物事に対して使う言葉なので、相手に使うのは失礼に当たります。
■ 欧州で『梯子の下を歩く』はタブー!
理由は、梯子の形が三角形であること、三角形は紀元前から生命のシンボルと信仰され、その三角形の領域に踏み込むことは、神聖なものを侵す行為とみなされるからです。
■ 中国の『闘茶』
日本の米の年貢制度のように、中国にもお茶を納める慣習があります。大昔、地方の小国が権力者に郷里の茶を納めた事が、やがてお茶の地位を競う『闘茶』になりました。
■ 夏は冷たくて冬は暖かい川?!
徳島県にある『江川』という川は、夏は約10度の冷たい湧水、冬は約20度の暖かい湧水になります。何故そうなるのか、原因は未だに解明されてないそうです。
■ 眠気は逆立ちで覚ませ!
眠気を一発で取る方法は、逆立ちがお勧めです。逆立ちにより脳へ多くの血液が送られ、血行が良くなり、新鮮な酸素や栄養が補給されるので、頭の中がすっきりします。
■ 住所が存在しない国『ドバイ』
ドバイ国民はもともと遊牧民で、定住する習慣がなかったため、住所は存在しません。尚、郵便物は自宅ではなく、郵便局や勤務先の私書箱に届けます。